蓄電池
蓄電池を設置することで、電気代の節約や災害時の備えができます。
一方で、初期費用や設置スペースなどの課題もあります。
蓄電池とは?
蓄電池とは、電気を蓄えて必要なときに使用できる装置のことです。家庭用蓄電池は、太陽光発電で作られた電気や、電力会社から購入した電気を貯めることで、夜間や停電時でも電気を利用できるようにする役割を果たします。従来は産業用が中心でしたが、近年では災害対策や電気料金の節約を目的に、一般家庭でも蓄電池の導入が進んでいます。特に、太陽光発電システムと組み合わせることで、より効率的に電気を自家消費できるようになります。

太陽光発電と蓄電池の仕組み
太陽光発電と蓄電池は、家庭の電力供給を効率的にサポートするためのシステムとして、特に注目されています。
太陽光発電は、太陽の光をエネルギーに変換するためのシステムで、日中に太陽の光を受けて発電します。
しかし、発電した電気はそのままでは夜間や天候不良時に使うことができません。
ここで重要になるのが、蓄電池の役割です。

太陽光発電の仕組み
太陽光発電は、屋根に設置されたソーラーパネル(太陽光パネル)が太陽の光を受けて電気を生み出します。これらのパネルは、光エネルギーを直接電気に変換する「太陽光発電セル」を使用しており、発電した直流電流(DC)は、インバーター(交流変換機)によって家庭で使用するための交流電流(AC)に変換されます。これで家庭内の電化製品を動かすための電力源となります。

蓄電池の仕組み
蓄電池は、太陽光発電で生み出された余剰電力を一時的に貯めておく装置です。昼間に発電した電気が使われない場合、余った電力を蓄電池に蓄え、夜間や日照の少ない時間帯に利用できるようにします。蓄電池は基本的にリチウムイオン電池や鉛蓄電池が使用されており、充電と放電を繰り返すことで電力を蓄えます。これにより、昼間に太陽光発電で作った電力を夜間に使用することができ、電力会社からの電力購入を減らすことが可能になります。

太陽光発電と蓄電池の連携
昼間は太陽光発電システムが稼働しており、発電された電力はまず家庭で使用され、余った分が蓄電池に蓄えられます。夜間になると、蓄電池から電力を取り出して使用するため、電力会社から購入する電力量を抑えることができます。特に電気代が高くなる時間帯(昼間のピーク時間や夕方から夜間にかけて)の使用を蓄電池で賄うことができれば、光熱費の節約につながります。
また、非常時や停電時の備えにもなります。発電した電力が蓄電池に蓄えられているため、停電時でも蓄電池に蓄えられた電力を使用して家庭内での電力供給を維持できます。特に蓄電池は、停電時におけるライフラインを確保する役割を果たします。



蓄電池のメリット
家庭用蓄電池の設置には、大きく分けて「節電による経済メリット」と
「非常用電源としての災害対策」という2つのメリットがあります。
節電による経済メリット
近年、売電価格の低下と電気料金の上昇により、発電した電力を売るよりも、自家消費するほうが経済的にお得になっています。
特に「卒FIT(固定価格買取制度の終了)」を迎える家庭では、売電価格が大幅に下がるため、
蓄電池の導入により電気代の削減効果がさらに高まります。
01 売電価格の低下と電気料金の上昇
電気料金を節約
かつては、太陽光発電で余った電力を固定価格買取制度(FIT)により売電することで、経済的なメリットがありました。しかし、売電価格の低下と電気料金の上昇により、発電した電気を自家消費するほうが経済的にお得になっています。具体的には、10年前(2015年度)の売電価格は33円/kWhでしたが2025年度の売電価格は6~10円/kWh程度になると予想され、卒FIT後はさらに自家消費のメリットが増します。一方、電気料金は30円/kWhから35円/kWhに上昇すると予想され、売電よりも自宅で消費した方が大きな経済効果を得られる状況となっています。

02 卒FIT後の経済メリット
FIT(固定価格買取期間)の買取期間(10年間)が終わると、売電価格は電力会社の 自由契約価格 となり、多くの家庭で 6~10円/kWh 程度にまで下落すると予想されています。 この価格で売電するより、電気料金30円/kWhを、発電した電力で消費するほうが3倍以上お得になります。つまり、蓄電池の導入コストを考慮しても、長期的には蓄電池を設置するほうが圧倒的に経済的メリットが大きいことがわかります。

01 非常用電源としてのメリット
例えば、2019年の千葉県台風では最長2週間の停電が発生しました。蓄電池がない家庭では、スマートフォンの充電のために 1日5時間以上並ぶ必要がありました。
蓄電池があれば、停電時でも照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電はもちろん、エアコンやIHクッキングヒーター などの200Vの家電も使用可能です。

02 蓄電池の稼働時間
家庭用蓄電池があれば、停電時でも電気を使うことができます。ただし、使用できる時間は蓄電池の容量や家電の消費電力によって異なります。
たとえば、7.0kWhの蓄電池なら冷蔵庫・照明・スマホ充電のみで約24時間、10.0kWhの蓄電池なら同じ条件で約36時間、16.0kWhの蓄電池なら約60時間使用できます。ただし、エアコンやIH調理器など消費電力の大きい家電を使うと、稼働時間は短くなります。

蓄電池の注意点
蓄電池には多くのメリットがある一方で、
導入前に注意点・考慮すべき点もあります。

ソーラーパネルとの適合性
既存のソーラーパネルと蓄電池の互換性を確認することが重要です。適切な蓄電容量やシステムの組み合わせを選ばないと、十分な効果を得られない可能性があります。

リチウムイオン電池の寿命
蓄電池は経年劣化により蓄電容量が徐々に低下します。一般的な家庭用リチウムイオン蓄電池の寿命は 10~15年程度 ですが、使用環境や充放電の頻度によって変動します。
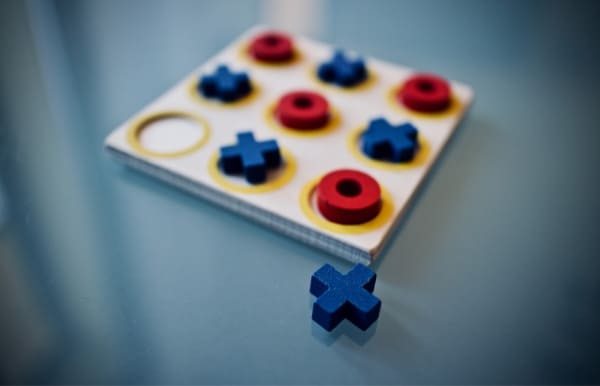
優良な販売・施工業者の選定
蓄電池の設置は専門知識が必要なため、施工の質によってはトラブルが発生することも。信頼できる業者を選ぶことが、長期的に安定した運用につながります。
蓄電池の導入費用
家庭用蓄電池を検討する際、多くの方が 「価格・蓄電容量」 に注目しがちですが、
「停電時の動作・寿命・性能」 も重要な要素です。
特に 非常時の電力供給 や 長期間の運用 を考えると、単に安い製品を選ぶのではなく、性能面も考慮して選ぶことが大切です。
蓄電池の価格と仕様
蓄電池は、メーカーや製品の種類によって価格が異なります。
家庭用蓄電池には、大きく分けて 「ハイブリッド型」 と 「単機能型」 の2種類があります。
以下は、いくつかのメーカーとその蓄電池の価格と特徴の比較です。(※価格は変動する場合があります)
01 ハイブリッド型蓄電池
効率的に電気を活用
ハイブリッド型蓄電池は、太陽光発電と蓄電池を1台のパワーコンディショナー(パワコン)で制御できるタイプです。
直流の発電電力を直流のまま蓄電池に充電できるため、電力変換のロスが少なく、効率的に電気を活用できます。
以下に、代表的なハイブリッド型蓄電池の仕様を比較します。

↓横にスクロールできます
| メーカー |

|
|

|

|

|

|

|
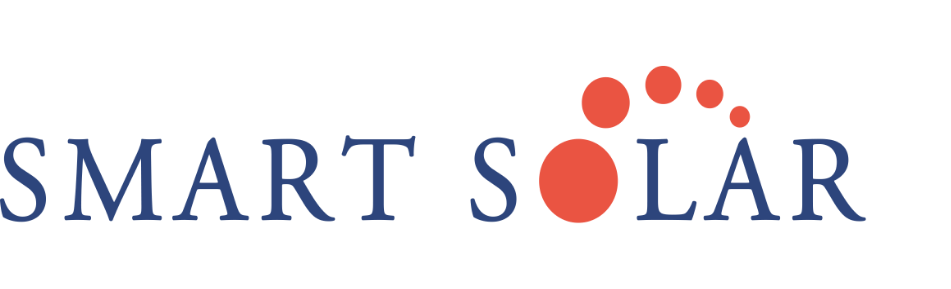
|

|

|

|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電容量(kWh) | 6.3 / 6.5 / 9.8 / 12.7 / 16.4 | 4.9 / 7.4 / 7.7 / 9.7 | 5.5 / 11 / 16.5 | 7.04 / 14.08 | 3.3 / 6.6 / 12.8 | 6.5 / 7.7 / 9.5 / 13 / 15.4 | 6.6 / 9.9 / 13.3 | 11.5 | 3.5 / 5.6 / 6.3 / 7 / 9.1 / 11.2 / 12.6 | 5 / 10 / 15 | 5.8 / 11.5 / 17.3 |
| 価格(定価) | 269万円 ~ 552万円 | 120万円 ~ 240万円 | 341万円 ~ 781万円 | オープン価格 | 209万円 ~ 418万円 | 315万円 ~ 412万円 | オープン価格 | オープン価格 | 204万円 ~ 285万円 | オープン価格 | オープン価格 |
| 停電時の出力 | 2.5kW ~ 5.0kW | 4.0kW ~ 5.9kW | 2.0kW ~ 4.5kW | 5.5kW | 6kW | 2.0kW ~ 4.0kW | 5.9kW | 3.0kW | 2.0kW ~ 4.0kW | 1.5kW ~ 4.5kW | 3kW ~ 5.9kW |
| 想定寿命 | 11,000サイクル | 20,000サイクル | 12,000サイクル | 11,000サイクル | 12,000サイクル | 12,000サイクル | 12,000サイクル | 8,000サイクル | |||
| 機器保証 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 10年(有償15年) | 10年 | 10年 | 15年 |
| おすすめポイント | ライフスタイルに合わせて容量と仕様を選択可能。コンパクトながら大容量モデルも。 | AIが最適な運転をサポート。設置後のV2H増設にも対応し、将来の拡張性が高い。 | 設置後でも容量の追加が可能。安全性の高いクレイ型セル採用で安心。 | 業界トップクラスの2万サイクル寿命。コストパフォーマンスに優れる。 | 1日2回の充放電が可能で、より効率的にエネルギー活用。見守りサービス付きで安心。 | 最大8.8kWの太陽光パネルに対応し、遠隔見守りサービスで安心の運用が可能。 | 豊富な蓄電容量ラインナップで、家庭の電力ニーズに合わせた選択が可能。 | コンパクトな設計で、省スペースに設置可能。 | 防水・防塵性能を備え、幅広い環境に対応。AIが自動で最適運転を行う。 | 2台設置で13kWhまで拡張可能。長期間の運用にも安心。 | スマートリモコン対応で、家電の一括操作が可能。よりスマートなエネルギー管理を実現。 |
02 単機能型蓄電池
後付けしやすい
単機能型蓄電池は、太陽光発電用と蓄電池用の2台のパワコンが必要になるタイプです。太陽光発電の電力をいったん交流に変換してから蓄電池に充電するため、変換ロスが発生します。しかし、既存の太陽光発電システムに後付けしやすいというメリットがあります。

↓横にスクロールできます
| メーカー |

|
|

|

|
|---|---|---|---|---|
| 蓄電容量(kWh) | 13.5 | 11.1 / 16.6 | 9.8 / 13.16 | 2.4 ~ 14.4 |
| 価格(定価) | オープン価格 | 370万円 ~ 450万円 | 330万円 ~ 373万円 | オープン価格 |
| 停電時の出力 | 5kW | 3kW | 3.0kW ~ 5.5kW | |
| 想定寿命 | 6,000サイクル | 6,000サイクル | ||
| 機器保証 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| おすすめポイント | 最大10台まで接続可能で、大容量の蓄電システムを構築可能。 | コンパクトサイズで狭小住宅にも設置しやすく、V2H連携にも対応。 | AI制御で最適な運転を実現し、電気代の削減にも貢献。 | 発電電力のみで充電でき、1~6台の自由な組み合わせが可能。 |
蓄電池の補助金・優遇制度
家庭用蓄電池の導入には、国や自治体の補助金制度や電力会社の優待プランを活用できる場合があります。
これらを上手に活用することで、初期費用を抑えながら導入が可能です。補助金の詳細や申請方法は年度ごとに変更されるため、
最新の情報を経済産業省や環境省の公式サイトで確認することをおすすめします。
1. 国の補助金制度
日本政府は、再生可能エネルギーの普及促進や災害時のエネルギー確保を目的に、
家庭用蓄電池の導入に対して補助金を提供しています。
現在利用可能な補助金には以下のようなものがあります。
(1) 需給一体型再エネ補助金(環境省)
太陽光発電と蓄電池を組み合わせた住宅向け補助金で、再生可能エネルギーを活用しつつ、電力の需給を最適化することを目的としています。補助額は設備容量や要件によって異なるため、詳細は公的機関の発表を確認する必要があります。
(2) 住宅省エネ支援事業(経済産業省・国土交通省)
住宅のエネルギー効率向上を目的とした補助金制度で、蓄電池を導入する際に適用できる場合があります。特に、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)対応住宅では補助の対象となるケースが多いです。
2. 自治体の補助金制度
全国の自治体では、地域ごとのエネルギー政策の一環として
蓄電池の導入補助金を提供している場合があります。補助額や条件は自治体ごとに異なり、
申請時期や受付期間が限定されていることが多いので、事前に確認しておくことが重要です。
(1) 補助額と条件
自治体の補助金は、一般的に1kWhあたり数万円の補助が受けられる形になっており、蓄電池の容量に応じて補助額が決まるケースが多いです。例えば、東京都の場合は最大数十万円の補助が受けられることがあります。
また、多くの自治体では、太陽光発電とセットで導入する場合に補助金が適用されるケースが多いため、既存の太陽光システムとの組み合わせを考えると、よりお得に導入できます。
(2) 申請方法
自治体の補助金は、申請期間が限られており、早期に予算が終了することもあるため、計画的に申し込むことが重要です。各自治体のホームページやエネルギー関連の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
3. 電力会社の優待制度
電力会社によっては、蓄電池を導入する家庭向けに特別な電気料金プランを提供している場合があります。
特に、夜間の安い電力を貯めて昼間に使用することで電気代を抑える仕組みを採用しているプランが多く、
うまく活用すれば経済的なメリットが大きくなります。
(1) 夜間電力の活用プラン
多くの電力会社が提供している「時間帯別電気料金プラン」を利用すると、夜間に安価な電力を蓄電池に充電し、昼間に使用することで電気料金を節約できます。
例えば、東京電力の「スマートライフプラン」は夜間の電気料金が割安になり、関西電力の「はぴeタイムR」は昼間の電気料金を抑えつつ深夜の電力を安く提供するなど、地域ごとに異なるプランが用意されています。
(2) VPP(仮想発電所)への参加
一部の電力会社では、VPP(仮想発電所)事業の一環として、家庭用蓄電池を制御し、電力の需給バランスを最適化する取り組みを行っています。VPPに参加すると、電力会社から報酬や特典が受けられる場合があります。
4. 住宅ローン減税・エコポイント制度
蓄電池の導入を含む省エネ住宅の改修や新築では、
住宅ローン減税やエコポイントの制度が適用されることがあります。
(1) 住宅ローン減税
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)対応の住宅を建てる場合、住宅ローン減税が適用される可能性があります。蓄電池を含む省エネ設備が導入されていれば、税制面でも優遇を受けられます。
(2) エコポイント制度
省エネリフォームやZEH化を促進するため、一定の条件を満たすとポイント還元を受けられる制度があります。蓄電池の設置が対象となる場合もあるため、各制度の詳細を確認するとよいでしょう。
 最新の補助金・優待情報を確認する方法
最新の補助金・優待情報を確認する方法
補助金や優遇制度は、年度ごとに変更されるため、以下の方法で最新情報をチェック するのがおすすめです。
・経済産業省・環境省の公式サイト(国の補助金情報)
・各自治体のエネルギー政策ページ(地域ごとの補助金情報)
・電力会社の公式サイト(売電価格や優待制度)
・補助金情報をまとめたポータルサイト(最新の補助金一覧)

蓄電池を導入する際には、国や自治体の補助金制度、電力会社の優待制度、税制優遇などを活用することで、初期費用を抑えながら導入が可能です。それぞれの制度には適用条件があるため、自分の住宅や契約状況に合った補助金を見極めることが大切です。
最新情報を随時チェックし、賢く補助金を活用して、より経済的に蓄電池を導入しましょう。
住まいのことでお困りの際は、
いつでもご相談ください。



