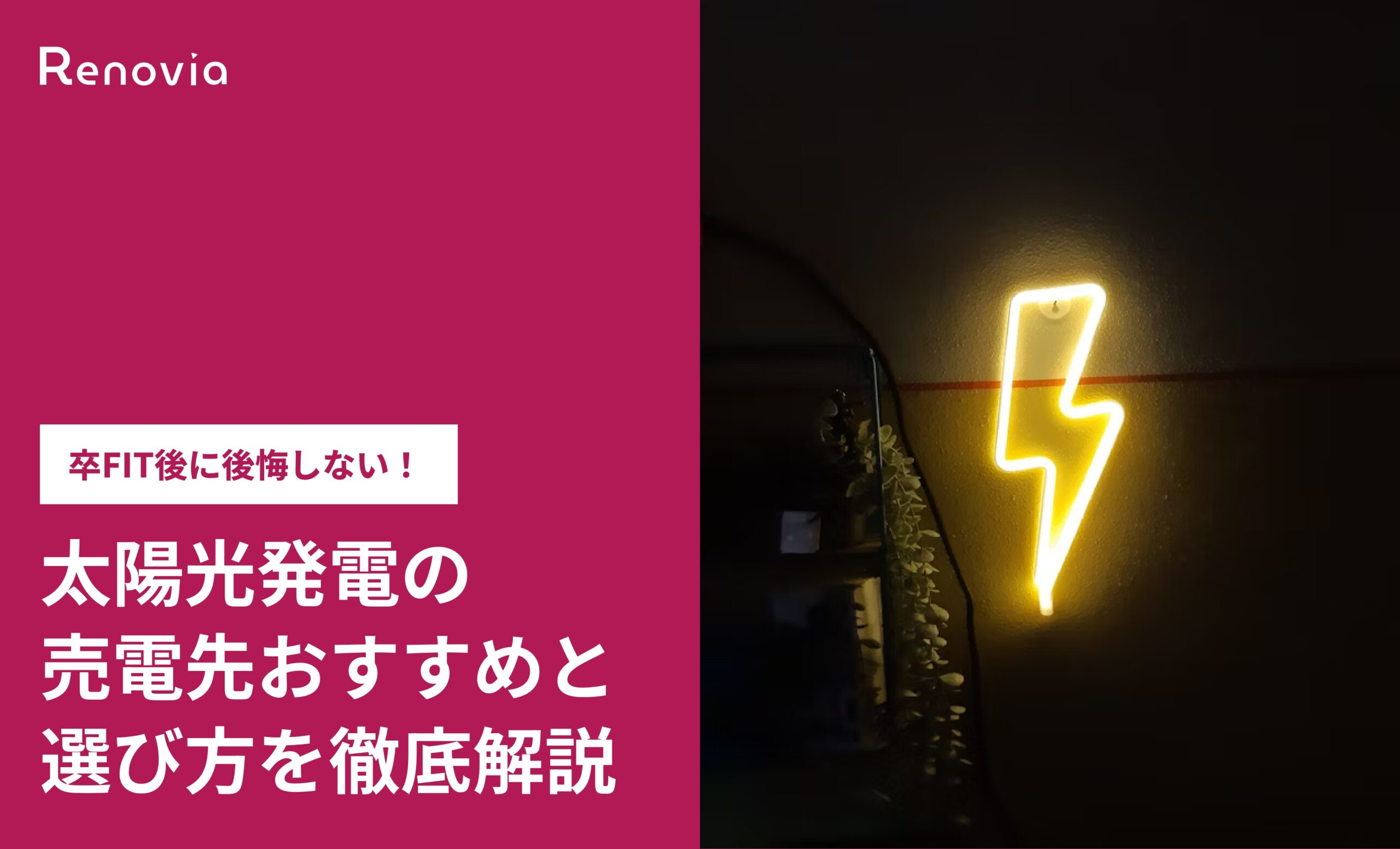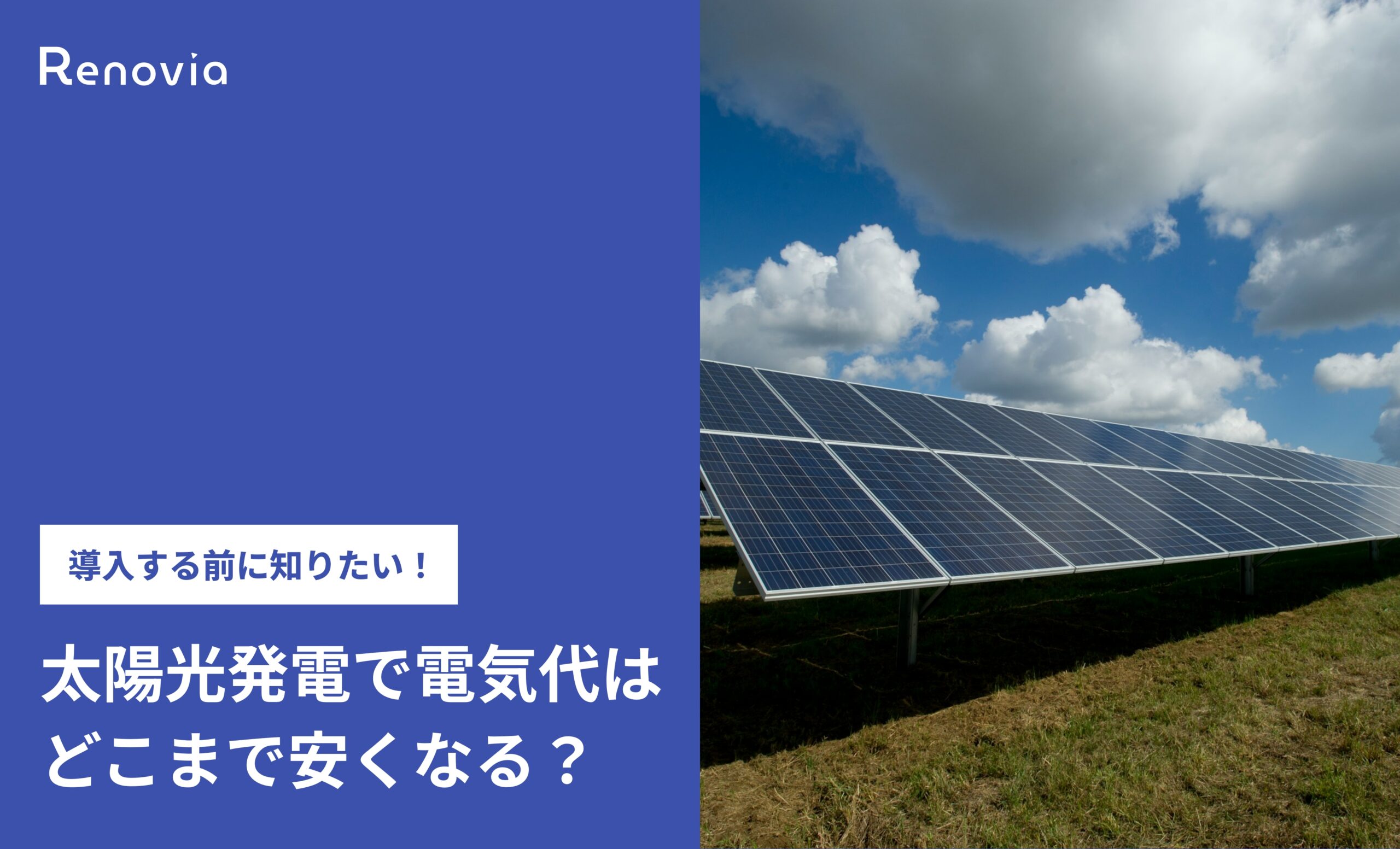目次
家庭用FIT制度の基礎知識

FIT制度とは?
FIT制度(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で一定期間、電力会社が買い取るよう義務づけたしくみです。2012年に導入され、特に家庭用太陽光発電(10kW未満)で普及を促進してきました。
ポイント
- 国による価格保証で初期投資の回収がしやすい
- 家庭用は10年間の買取期間が安定の基盤
- 再エネ普及を後押しする役割を果たした
家庭では「余った電気を売れる安心感」が最大のメリットでした。
FIT導入の背景
制度導入の背景には以下のような要因があります。
- 東日本大震災後の電力供給の不安から再エネの注目が高まった
- 脱炭素・国際的な再エネ導入圧力を受け、日本も導入を加速
- 太陽光関連産業育成、地域活性化の狙いもあった
こうした流れの中、家庭レベルでも太陽光導入が急速に進んでいきました。
家庭用FITの仕組み
以下の流れで太陽光発電が行われ、売電されます。
- 太陽光パネルで発電
- 家庭内で使用
- 余剰分を電力会社へ売電
- 10年間、国が定めた固定価格で買取
たとえば導入直後の2012年度には42円/kWhと高額だったため、売電で電気代を上回る収入を得る家庭もありました。
年度ごとの売電価格(10kW未満・住宅用)
| 年度 | 売電価格(税込・1kWh) | コメント |
|---|---|---|
| 2012年度 | 42円 | 導入時の「太陽光バブル」期 |
| 2016年度 | 約31~33円 | 設置費用低下にともない段階的引下げ |
| 2023年度 | 16円 | 半分以下に減少 |
| 2025年度上半期 | 15円 | 通常のFIT価格 |
| 2025年度下半期 | 初期投資支援型:24円(〜4年)、8.3円(5〜10年) | 支援スキーム導入 |
このように、導入年度や時期によって収益性に大きな差があります。
FITのメリットと限界
メリット
- 売電収入で設置費用を回収しやすい
- 10年間の買取価格が確定しているため安心
- 再エネ普及に直接貢献できる社会的意義
限界・課題
- 年々引き下げられる価格によって収益性の低下
- 契約終了後(卒FIT)は売電方法を自分で選ぶ必要がある
- 制度費用は再エネ賦課金として電気料金に上乗せされ、国民負担となる
2026年度からのFIT制度の変更点
2026年度以降、FIT制度には新たな「初期投資支援スキーム」が導入され、価格構造が見直されます。
- 10kW未満(住宅用):初期4年間は 24円/kWh、5〜10年目は 8.3円/kWh
- 10kW以上(事業用 屋根設置):初期5年間 19円/kWh、6〜20年目 8.3円/kWh
これは、導入初期に収益を得やすくすることで投資回収を支援する設計です。
現在のトレンド:自家消費と蓄電池
FIT買取価格の低下を背景に、家庭用太陽光の使い方は「売る」から「使う」へと大きく変化しています。
代表的なトレンド
- 蓄電池の普及:昼間の電気を貯めて夜間に消費、電気代削減や停電対策にも有効
- V2H(Vehicle to Home):EVを家庭の電源として活用する動きが広がる
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム):電気を「見える化」し賢く制御・活用
- 地域電源との連携:VPPやスマートシティ構想への参加など、新たな取り組みも進展
特に、2026年度以降は「一定の高価格で売電できる前半だけ稼いで後は使う」という戦略が一般的になります。
2026年度からのFIT制度変更点
FIT縮小の流れと国の方針
家庭用FIT制度は2012年に始まり、普及を大きく後押ししてきました。しかし導入から10年以上が経過し、国は「市場に任せられる段階」に入ったと判断しています。そのため、2026年度からは従来型の固定買取制度を大きく見直し、より自立的な運用を促す方針です。
ポイント
- 従来型の高単価・長期保証は縮小
- 市場価格に近づける仕組みに移行
- 自家消費重視の制度へシフト
新しい買取価格の仕組み
2026年度からは「初期投資支援型」のFIT制度が導入されます。これは、導入直後の数年間に高い単価を設定し、投資回収を後押しする代わりに、その後は低単価へ切り替える方式です。
家庭用(10kW未満)の買取価格(2026年度以降)
| 期間 | 単価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| 1〜4年目 | 24円/kWh | 初期投資回収をサポート |
| 5〜10年目 | 8.3円/kWh | 市場価格に近い水準へ移行 |
事業用(屋根設置・10kW以上)の場合は初期5年間19円、その後は20年間8.3円という設計です。
従来のように「10年間すべて一定の高単価で保証」ではなくなる点が大きな変化です。
既存契約者への影響
すでにFIT契約を結んでいる家庭には直接的な変更はありません。契約時点の単価と期間がそのまま適用されます。ただし、2016年度に認定を受けた家庭が2026年度に多数卒FITを迎えるため、売電単価は市場水準(10円前後)に下がる見込みです。
卒FITを迎える家庭の選択肢
- そのまま市場価格で売電する
- 新電力の卒FITプランに切り替える
- 蓄電池を導入して自家消費に回す
- EVやV2Hを活用し電力の有効利用を図る
制度変更の背景
国がこのような制度変更に踏み切る背景には次の理由があります。
- 発電コストの低下により、高額の買い取りを続ける必要がなくなった
- FITコスト(再エネ賦課金)の国民負担が増大している
- 電力市場全体で再エネを自立的に運用する段階に入った
つまり「補助的なFIT」から「自立した再エネ利用」へと移行する過程といえます。
家庭が取るべき対応
2026年度以降は「売電で儲ける」より「家庭で使って節約する」方向に戦略を変える必要があります。
考えられる対応策
- 蓄電池の導入で昼夜の電力をシフトし、電気代削減
- EV・V2Hを活用して電気の使い道を拡大
- HEMSを導入して電力利用を最適化
- 卒FIT後の売電先を早めに検討
制度の変化はリスクでもありますが、家庭のエネルギー自給率を高めるチャンスでもあります。
卒FIT家庭の選択肢
卒FITとは?

家庭用FIT制度では、売電期間は10年間と定められています。この期間を過ぎると固定価格での買い取りは終了し、市場価格に基づく売電へ移行します。この状態を「卒FIT」と呼びます。
卒FIT後はこれまでのように高い単価での売電は期待できず、一般的に10円前後の市場価格での取引となります。そのため、家庭は「電気をどう扱うか」を改めて考える必要があります。
卒FIT後の売電先
卒FITを迎えた家庭は、売電先を自由に選べるようになります。主な選択肢は以下の通りです。
- 大手電力会社:既存の契約先で継続売電可能
- 新電力会社:卒FIT専用の買い取りプランを提供
- 地域電力・協同組合:地域内消費や地産地消モデルに参加
- P2P取引:ブロックチェーン技術などを活用し、個人間で売買する仕組み
それぞれのプランは価格や契約条件に差があり、比較検討が不可欠です。
卒FITプランの実例
大手電力や新電力では、卒FIT家庭向けにさまざまなプランが用意されています。
例:2024年時点の卒FITプラン(代表的なケース)
| 事業者 | 卒FIT買い取り価格 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大手電力A社 | 8〜10円/kWh | 契約継続が簡単 |
| 新電力B社 | 12円/kWh | 他社より高めの単価設定 |
| 地域電力C社 | 10円/kWh+地域ポイント | 地域貢献型モデル |
| 新興D社(P2P) | 変動(市場価格連動) | 将来的に成長が期待される仕組み |
選択肢が多様化する一方で、「条件のわかりにくさ」や「サービスの安定性」には注意が必要です。
自家消費という選択肢
売電単価が下がることで、「売る」より「使う」ほうが経済的になるケースが増えています。
自家消費を拡大する方法
- 蓄電池を導入して昼間の電気を夜に回す
- EVを導入し、家庭で充電・利用
- HEMSを活用して電気使用を最適化
- エコキュートやIH調理器などと連携させ効率的に利用
自家消費を強化することで、電気代削減効果を最大化でき、災害時の備えにもなります。
卒FITで注意すべきポイント
卒FITを迎える際には、以下の点に注意が必要です。
- 売電価格だけでなく契約条件(手数料、契約期間)を確認する
- 新電力の場合は倒産リスクやサービス継続性も考慮する
- 自家消費に移行するなら蓄電池やEVの初期投資コストを試算する
- 補助金や自治体の支援策が利用できるか確認する
卒FITは単なる「売電終了」ではなく、家庭のエネルギー戦略を見直す大きな転機といえます。
家庭用太陽光の最新トレンド

蓄電池導入の加速
FIT価格の低下や電気料金の上昇を背景に、家庭での自家消費を高めるために蓄電池の導入が進んでいます。発電した電気を夜間に回すことで電気代を抑えられるほか、停電時のバックアップ電源としても有効です。
蓄電池導入のメリット
- 昼夜の電力利用を平準化し、電気代削減につながる
- 停電や災害時の非常用電源になる
- 再エネの自家消費率を高め、卒FIT後も有効活用できる
導入コストは100〜150万円前後が主流で、国や自治体の補助金を活用すれば負担を軽減できます。
EV・V2Hを活用した電力利用
電気自動車(EV)の普及に伴い、EVを家庭の電源として活用する「V2H(Vehicle to Home)」が注目されています。EVは大容量のバッテリーを備えているため、家庭の電気を丸1日以上まかなえる場合もあります。
V2Hの活用例
- 昼間に太陽光で発電した電気をEVに充電
- 夜間や停電時にEVから家庭へ電力を供給
- 電気料金の安い深夜電力を充電して昼間に利用
EVと太陽光・蓄電池を組み合わせることで「走る蓄電池」としての役割を果たし、家庭の電力自給率が大幅に高まります。
HEMSによる電力管理
HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)は、家庭の電気の使い方を「見える化」し、自動制御で最適化する仕組みです。スマホアプリからリアルタイムに電気使用状況を確認でき、蓄電池やEV、家電を連動させることも可能です。
HEMS導入の効果
- 発電量と消費量を最適にコントロール
- 電気料金のピークを避けて節約
- 家電や給湯機を自動制御し効率的に利用
家庭のエネルギー管理を高度化することで、自家消費の最大化が可能になります。
地域分散型エネルギーとの連携
近年は、家庭用太陽光が「単独で使う」だけでなく、地域エネルギーの一部として活用される動きも進んでいます。
代表的な取り組み
- VPP(仮想発電所):複数の家庭の蓄電池を束ねて大きな電源として扱う仕組み
- スマートシティ:地域全体でエネルギーを効率的に利用する街づくり
- 地域新電力:地元の発電を地元で消費し、地域経済を循環させるモデル
これらの取り組みに家庭が参加することで、環境負荷の低減だけでなく地域貢献にもつながります。
「売る」から「貯めて使う」へのライフスタイル変化
従来の太陽光発電は「売電による収益」を前提にしたものでした。しかし、FITの縮小や電気料金の上昇により、「自分の家で使って節約する」方向へと変化しています。
ライフスタイルの変化
- 電気は売るよりも家庭で使うほうがメリットが大きい
- 蓄電池やEVを組み合わせて自給自足を強化
- エネルギーを意識した暮らしが日常化
こうした変化は「ポストFIT時代」の大きな特徴であり、家庭が主体的にエネルギーを管理する時代の幕開けといえます。
導入費用と投資回収のシミュレーション

太陽光パネルの設置費用
家庭用太陽光パネルの設置費用は年々下がってきたとはいえ、依然として大きな投資です。かつては1kWあたり40〜50万円かかっていましたが、現在は20〜25万円前後が主流となっています。
例:家庭用(4〜5kW規模)の設置費用相場
- 2012年頃:150〜200万円
- 2020年頃:120〜150万円
- 2025年現在:130〜170万円
価格低下の要因
- パネルの大量生産によるコスト削減
- 施工効率の改善
- 競争激化による価格調整
それでも家庭にとっては依然として大きな出費であり、投資回収を見据えた導入計画が求められます。
蓄電池・V2H導入コスト
自家消費を最大化するための蓄電池やV2Hも、高額な投資対象です。
蓄電池の導入費用(2025年時点)
- 小型(4〜6kWh):120〜150万円
- 中型(7〜10kWh):150〜200万円
- 大型(10〜15kWh):200〜260万円
V2Hシステムの導入費用
- 専用機器+工事費:120〜170万円
- EV本体を含めるとさらに数百万円規模
補助金を組み合わせれば実質的な負担を軽減できますが、初期投資としては依然ハードルの高い金額です。
売電収入と自家消費効果
2026年度以降のFIT制度では、売電単価が前半4年間は24円、後半は8.3円に下がります。従来のように「売電で設置費用を回収する」考え方は通用しにくくなり、自家消費を中心に経済効果を得る形へ移行します。
試算例(5kWシステム導入・年間発電量5,500kWh想定)
- 自家消費率50%、電気代単価30円/kWhの場合
→ 年間約8.2万円の電気代削減 - 売電(残りの50%を平均15円で売却)
→ 年間約4.1万円の売電収入 - 合計効果:約12.3万円/年
導入費用を150万円とした場合、単純回収年数は約12年前後となります。
投資回収期間のシミュレーション
蓄電池を組み合わせると導入コストはさらに増えますが、停電リスクや電気料金上昇を踏まえると長期的な価値は高まります。
回収期間の目安
- 太陽光パネル単体:10〜12年
- 太陽光+蓄電池:14〜16年
- 太陽光+蓄電池+V2H:16年以上(ただし災害対応力は格段に向上)
電気料金の上昇や補助金の適用次第では、回収期間は数年短縮される可能性があります。
2026年度以降の投資判断のポイント
FIT縮小後も太陽光発電は有効な選択肢ですが、「儲けるため」ではなく「暮らしを守るための投資」として考えることが重要です。
チェックポイント
- 補助金をどこまで利用できるか
- 自家消費率を高める工夫(蓄電池・HEMS・EV)をどう組み合わせるか
- 導入規模を家庭のライフスタイルに合わせて適正化できているか
- 回収年数だけでなく災害対応力・将来の電気料金リスクも考慮するか
「初期投資はやや高いが、長期的に見れば家計と安心を支える仕組み」として検討する姿勢が求められます。
補助金・火災保険・税制優遇の活用

補助金制度の概要
太陽光発電や蓄電池の導入には100万円を超える大きな初期投資が必要ですが、国や自治体の補助金をうまく活用すれば、実質的な負担を大幅に抑えることが可能です。
近年は自治体独自の補助金が充実しており、条件によっては「自己負担ほぼゼロ」で太陽光や蓄電池を設置できるケースも出てきています。特に都市部では、国の補助金と組み合わせて数十万〜100万円超の支援を受けられる事例も珍しくありません。
主な補助金の特徴
- 国の補助金:蓄電池やV2Hなど、自家消費を高める設備に重点
- 自治体の補助金:太陽光パネルや蓄電池に高額支援を実施する自治体もあり
- 期間限定の大型支援:年度末や特定プロジェクトに集中して実施されることもある
地域によって補助額や条件は異なりますが、調べてみると「導入費用の大半をカバーできる」ケースは意外に多く存在します。
火災保険でカバーできる範囲
太陽光パネルは屋根に設置されるため、台風や落雷など自然災害の影響を受けやすい設備です。火災保険や地震保険を活用することで、不測のトラブルに備えることができます。
火災保険で補償される主なケース
- 台風・雹・落雷による破損
- 火災による焼失・損傷
- 雪の重みでの破損
ただし経年劣化や施工不良による故障は対象外となることが多いため、メンテナンス契約との併用が望ましいです。
税制面でのメリット
太陽光発電や蓄電池には税制優遇措置も存在します。個人事業主や法人の場合は減価償却や控除制度が利用でき、家庭でも自治体によっては固定資産税の軽減措置が設けられる場合があります。
税制優遇の例
- 中小企業経営強化税制:対象設備の即時償却や特別控除が可能
- グリーン投資減税:再エネ関連設備への投資に優遇措置
- 固定資産税の軽減:一部自治体が導入している特例
こうした制度は年度ごとに変わるため、導入時点で最新情報を確認することが重要です。
補助金・保険・税制を活用する際の注意点
お得に見える制度も条件が細かく、申請方法も複雑なことがあります。
注意すべきポイント
- 補助金は予算が限られており、先着順や抽選制が多い
- 複数の補助金を同時に併用できない場合がある
- 火災保険の補償範囲は契約ごとに異なる
- 税制優遇は対象が限定されるため要確認
上手に制度を組み合わせれば、実質的な手出しを大幅に削減し、場合によってはほぼゼロで導入できるケースもあります。これらを知らずに導入するのは非常にもったいないといえます。
トラブル事例と注意点

発電量が期待より少ないケース
太陽光発電の導入後、「思ったより発電しない」と感じる家庭も少なくありません。原因はさまざまで、事前のシミュレーションと実際の環境条件に差があることが多いです。
発電量が減る主な要因
- 屋根の向きや角度が最適化されていない
- 周囲の建物や樹木による影の影響
- パネルの汚れや経年劣化
- システム容量に対して使用量や売電計画が合っていない
導入時には、年間の日射量データや周囲環境をしっかり調査することが欠かせません。
売電契約に関するトラブル
FITや卒FITでの売電契約に関しても注意が必要です。
よくあるトラブル
- 想定していた売電価格と実際の価格が違う
- 契約更新の条件がわかりにくい
- 新電力会社が倒産・撤退して売電先を失う
- 契約解除時の違約金や手数料が発生
契約書をよく確認し、不明点は事前に業者や電力会社に問い合わせることが大切です。
メンテナンス不備によるリスク
太陽光発電は基本的にメンテナンスフリーと思われがちですが、実際には定期点検や清掃が必要です。
メンテナンスを怠ると起きやすいトラブル
- パネルの劣化・出力低下
- パワーコンディショナーの故障
- 配線の不具合や接触不良
- 発火事故につながるケースもある
定期点検の目安は4〜5年に1回程度。長期的に安心して使うためには、点検契約を結んでおくのが望ましいです。
悪質業者や訪問販売への注意
太陽光発電の普及とともに、悪質な販売手口も問題となっています。特に訪問販売や電話勧誘による契約トラブルが後を絶ちません。
典型的な手口
- 「今なら補助金が必ず出る」と誤解を与える説明
- 「絶対に元が取れる」と過度に楽観的なシミュレーションを提示
- 施工やアフターサービスの質が低い
契約を検討する際は複数業者から見積もりを取り、信頼できる施工業者を選ぶことが不可欠です。
長期利用のために必要なチェックポイント
安心して長期間利用するために、以下の点を確認しておくとトラブルを防ぎやすくなります。
チェックポイント
- 契約内容(売電単価、期間、更新条件)を把握する
- 補助金や保険の利用条件を確認しておく
- 信頼できる業者かどうかを口コミや実績で確認する
- 定期点検・メンテナンス体制が整っているか確認する
- 卒FIT後の売電先や自家消費プランをあらかじめ検討しておく
こうした準備をしておけば、トラブルを最小限に抑え、長期にわたって安定した発電ライフを楽しむことができます。
これからの家庭用太陽光の展望
脱炭素社会における家庭の役割
日本は2050年カーボンニュートラルを掲げており、再生可能エネルギーの導入拡大は避けられない課題です。家庭用太陽光はその中で「分散型電源」として重要な役割を担います。家庭ごとに発電と消費を行うことで、大規模発電所への依存を減らし、エネルギーの自立性を高められます。
家庭が果たす役割
- 自家消費による温室効果ガス削減
- 地域分散型エネルギーの一部としての貢献
- 災害時のレジリエンス強化
再エネは「国の施策」から「家庭の実践」へと主体が移りつつあります。
再エネ比率拡大と国の政策動向
政府は2030年度までに再エネ比率を36〜38%へ引き上げる目標を掲げています。その実現に向け、家庭用太陽光の普及促進は欠かせません。
国の動き
- 新築住宅への太陽光設置義務化(東京都など一部地域で先行)
- 補助金の重点化(蓄電池・V2H・HEMSなど自家消費設備にシフト)
- 電力市場と連動した新しい売電モデルの検討
2026年度以降のFIT縮小は、こうした政策の流れを後押しするものといえます。
スマートシティ・地域エネルギーネットワークとの連携
家庭用太陽光は、単独で使うだけでなく地域社会のエネルギー基盤の一部として活用される方向に進んでいます。
代表的な取り組み
- スマートシティ:住宅・商業施設・交通が一体でエネルギーを効率利用
- VPP(仮想発電所):家庭の蓄電池やEVを束ねて電力需給の調整に活用
- 地域新電力:地産地消モデルで地域の経済循環を支援
家庭の設備がネットワーク化されることで、エネルギーの効率性と安定性が一気に高まります。
「発電する家庭」から「エネルギーを管理する家庭」へ
これまで家庭用太陽光といえば「電気を発電して売る」ことが中心でした。しかし今後は、発電に加えて「いかに賢く使い、管理するか」が重視されます。
未来の家庭像
- 太陽光+蓄電池+EVを組み合わせ、自給率を高める
- AIやHEMSを活用し、電力使用を自動で最適化
- 地域ネットワークと連携し、余剰電力を効率的にシェア
「売電収入を得る家」から「エネルギーを自ら設計・活用する家」へ。この転換がポストFIT時代の大きな特徴です。
展望
FIT制度の縮小は、一見すると家庭にとって不利に見えます。しかし、電気代の高騰や災害対策を考えれば、太陽光と自家消費設備の価値はむしろ高まっています。2026年度以降は「電気を売る」から「電気を賢く使う」時代へと進み、家庭はエネルギーの主体として新しい役割を担っていくことになるでしょう。
弊社は全国対応で、住宅リフォームを中心とした各種サービスを提供しております。
経験豊富なアドバイザーが無料で現地調査を行い、お客様のご要望やお悩みに沿った最適な施工プランをご提案いたします。大規模な改修から小さな修理まで、精鋭の営業スタッフと熟練の職人チームが一丸となって、迅速かつ丁寧に対応いたします。
また、太陽光発電や蓄電池、エコキュートをはじめとした省エネ設備の導入や光熱費削減につながる断熱リフォーム、環境負荷の少ない住宅づくりにも力を入れております。これからの時代に欠かせない“エコリフォーム”をお考えの方にも、しっかりと対応可能です。
- 修理できるのかを知りたい…
- 外壁塗装の仕上がりイメージがつかない…
- 火災保険を使える修理なのか知りたい…
- 雨漏りしていて困っている…
- 屋根の老朽化が気になる…
- カビや結露が発生しやすい…
- 光熱費を抑えたいので断熱リフォームを考えている…
- 電気代が上がってきたので、太陽光発電や蓄電池を検討している…
- エコキュートの使い方や買い替え時期に悩んでいる…
- 省エネリフォームの補助金について詳しく知りたい…
このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に無料の現地調査をご依頼ください。
リフォームも、エコも、お住まいのことならすべて弊社にお任せください!